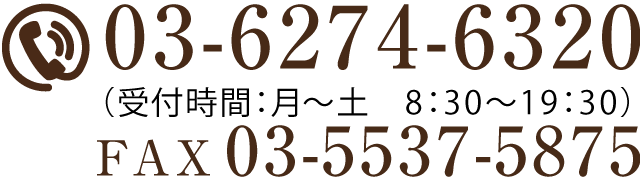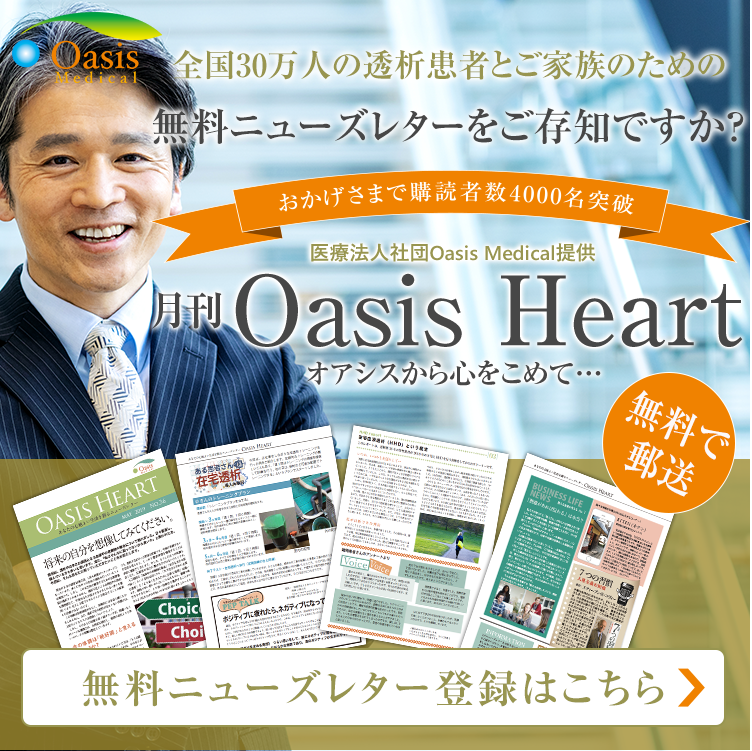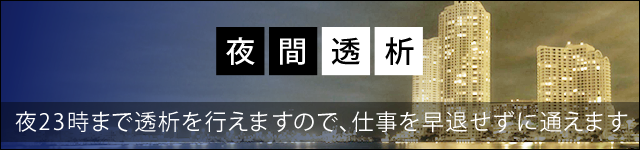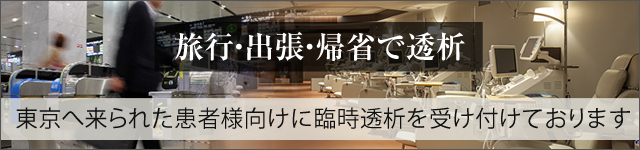透析で使われる「フサン」とは?その役割・特徴・注意点を解説
透析治療で回路やダイアライザー内で血液が固まらないように使われるのが抗凝固薬です。一般的にはヘパリンが用いられますが、出血リスクが高い場合やヘパリンが使えない場合は「フサン(ナファモスタットメシル酸塩)」が選択されることがあります。本記事では、フサンの役割や特徴、使われるケース、ヘパリンとの違いや使用する際の注意点についてお伝えします。
透析でフサンが使われるケースとは?
フサン(一般名:ナファモスタットメシル酸塩)は、血液透析で用いられる抗凝固薬の一つです。透析中、血液がダイアライザー(人工腎臓)や血液回路内で固まらないように使用されます。
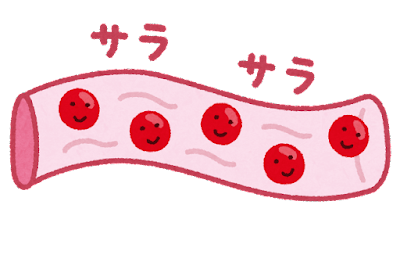
出血リスクが高い場合
消化管出血や脳出血の既往、手術直後などで出血リスクが高い症例に適しています。フサンは半減期が8分と短く、透析終了後には抗凝固作用がすみやかに減弱するため、出血リスクを抑えられるのが特徴です。
長時間の抗凝固作用を避けたい場合
作用時間が短時間のため、透析終了後すぐに手術や処置、検査が予定されているときなどに選択されます。
ヘパリン使用が禁忌の場合
ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)など、ヘパリンが使えない患者さんに対して使用する場合があります。
フサンは血液回路やダイアライザー内で凝固を起こりにくくし全身への作用時間は短時間です。出血リスクが高い方やヘパリンが使用できない方に用いられます。
フサン透析のメリット・デメリット
フサンを抗凝固薬として使用する透析のメリットとデメリットを説明します。
フサンのメリット

出血リスクを減らせる
フサンは体の中に長く残らず、透析回路の中だけで働きやすいため、透析後も薬の作用が残って出血が続くリスクが低くなります。
薬の作用が比較的短い
体の中に入ってもすぐに分解・排出されるため、透析を終えてから薬の作用が長く続くことはありません。
ヘパリンの副作用が避けられる
ヘパリン特有の副作用(骨がもろくなる、高脂血症、血小板減少など)が起こりにくくなります。
透析時のショックを低減できる
血液を体外に出したときに活性化する酵素や炎症反応を抑える作用があり、透析時のショック症状の低減が期待できます。
フサンのデメリット

薬価が高い
ヘパリンに比べて薬価が高く、医療費が高くなる場合があります。
使えない透析膜がある
特定の種類の透析膜(AN-69膜など)には薬が吸着されてしまい、十分な効果が得られないことがあります。
一部の治療器材で効果が弱まる
活性炭や特定の吸着カラムを使う治療(吸着療法)では十分に効果が出ない場合があります。
カリウム値の上昇
長時間使うと血中カリウム値が高くなることがあるため注意が必要です。
免疫の働きに影響する可能性
体の免疫細胞が炎症を起こす物質(インターロイキン-1)をいつもより多く作る可能性があり、長期的な経過を注意してみる必要性があります
ヘパリンとの違い
フサンとヘパリンには、作用の仕方や安全性、費用面でいくつかの違いがあります。以下に違いを表の形で整理しました。
| 項目 | フサン | ヘパリン |
|---|---|---|
| 作用の仕方 | 主に透析回路内で作用 | 全身 |
| 半減期 | 約8分 | 約1時間 |
| 出血リスク | 透析後はほぼなし | 透析後も注意が必要 |
| コスト | 高め | 安価 |
フサンは主に透析回路内で作用し、体内に入っても短時間で分解されます。半減期はおよそ8分と短く、透析終了後にはフサンの作用は長く残らないため、出血を軽減できます。
一方、ヘパリンは全身に作用し、半減期は約1時間です。そのため、透析後もしばらく血液が固まりにくい状態が続くため、出血には注意が必要です。また、費用面ではフサンは比較的高価で、ヘパリンは安価という特徴があります。
まとめ
フサン(一般名:ナファモスタットメシル酸塩)は短時間で作用が薄れる抗凝固薬で、出血リスクの高い透析患者さんに選択される場合があります。ただし、特定の透析膜や透析条件によって十分な効果が得られない場合があるため、使用時には注意が必要です。透析治療で使用する抗凝固薬の種類は、透析患者さんの病状やリスクを踏まえて医師が判断します。
※コラムに関する個別のご質問には応じておりません。また、当院以外の施設の紹介もできかねます。恐れ入りますが、ご了承ください。
※当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。