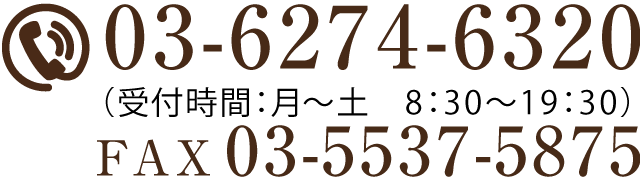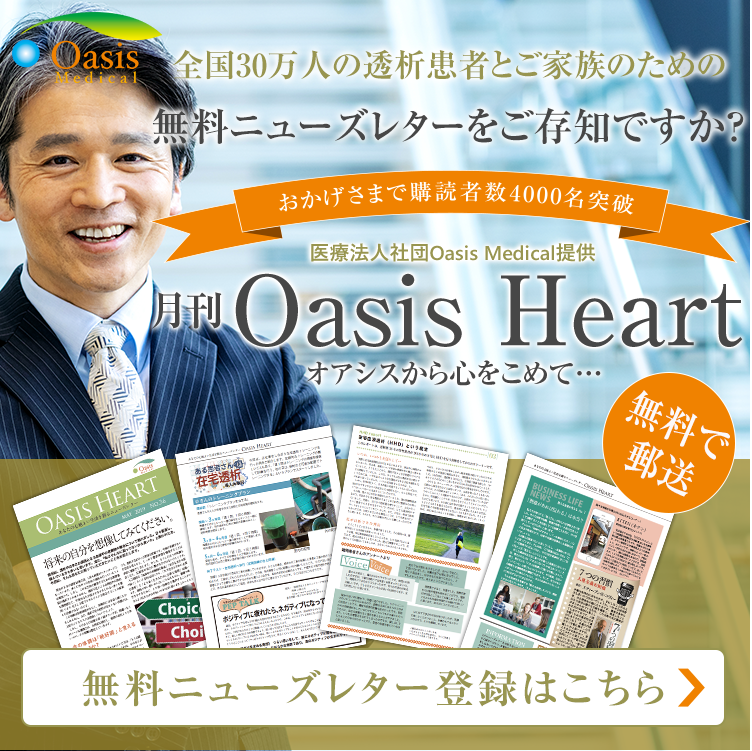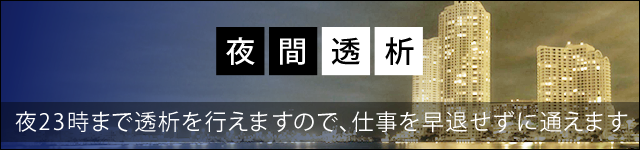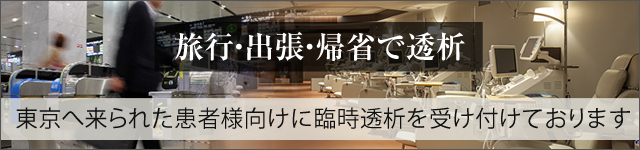【透析患者さん向け】ブラッドアクセスの種類と長持ちさせるための工夫
透析治療は、腎臓の働きが低下した患者さんが生命を維持するために欠かせない治療です。その透析を続ける上で大切になるのがブラッドアクセスと呼ばれる血液の出入口です。ブラッドアクセスの状態が悪化すると透析効率が落ち、場合によっては再手術が必要になることもあります。
この記事では、ブラッドアクセスの基本から種類ごとの特徴、選び方のポイント、そして長持ちさせるための管理やケア方法までをまとめました。透析を安定して継続していくための参考にしてください。
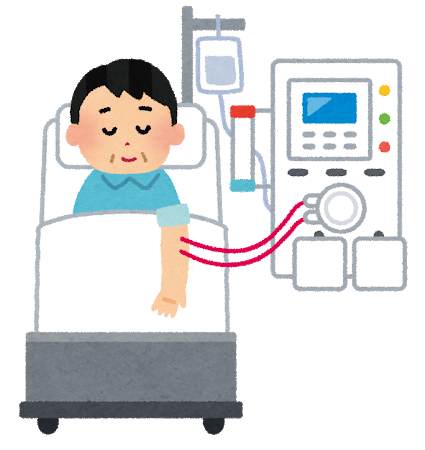
ブラッドアクセスとは?
ブラッドアクセスとは、 透析を行う際に血液を体外へ取り出し、再び体内に戻すための血管の出入口です。十分な血流量を確保できるかどうかが透析の質に関わります。
主な種類として以下の3つがあります。
内シャント(AVF:動静脈瘻)
自分の腕の動脈と静脈を手術でつなぎ合わせて作る方法で、もっとも一般的です。長期的に安定しやすく、感染リスクが比較的低いとされています。
人工血管グラフト(AVG)
自分の血管だけでは十分なアクセスが作れない場合に、人工血管を用いて動脈と静脈をつなぐ方法です。比較的早く使用開始できますが、血栓や感染のリスクがやや高めです。
カテーテル(CVC:中心静脈カテーテル)
頸部や鎖骨下にカテーテルを留置する方法です。緊急透析などで一時的に使われることが多く、感染リスクが高いため長期使用は推奨されません。
ブラッドアクセスの選び方
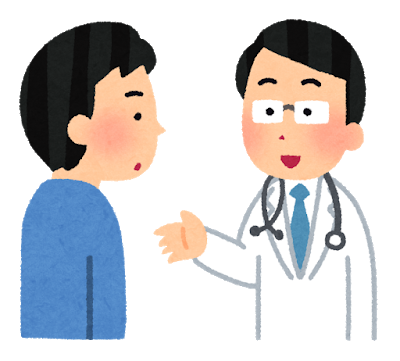
どのブラッドアクセスを選ぶかは、 血管の状態や年齢、合併症の有無などによって総合的に判断されます。
血管の太さや質
腕の血管がシャント作成に適した太さや状態である場合は、長期的なメリットが大きい内シャントが選ばれるケースが多い傾向です。
全身状態や透析導入の緊急性
心臓の機能が著しく低下している場合や、緊急で透析を始める必要がある場合は、手術の負担が少なく、すぐに使用できるカテーテルが一時的に用いられます。
合併症や既往歴
糖尿病による血管の損傷が進んでいる場合や、過去の手術歴なども考慮され、適切な方法が選択されます。
ブラッドアクセスの管理・ケアについて
ブラッドアクセスを長持ちさせるためには毎日のケアが重要です。

観察
毎日の観察で、ブラッドアクセスの状態をご自身で確認する習慣をつけることが大切です。シャント部分にそっと手を置き、血流による振動(ザワザワした感じ)を感じたり、音を聞いたりして、いつもと変わりがないかを確認しましょう。 音が弱くなったり振動が感じられなくなったりした場合は、血流に問題が起きているサインの可能性があります。
清潔の保持
穿刺する部位の周辺を清潔に保つことは、感染を予防するための基本です。透析当日の入浴は穿刺部から細菌が入る可能性があるため避けましょう。透析のない日に入浴やシャワーをする際には、石鹸をよく泡立て、手のひらでシャント部分をやさしく洗い、その後はよく乾かしましょう。
穿刺部の傷や皮膚の異常(赤み、腫れ、熱感、痛みなど)に気づいた場合は、速やかに医療スタッフに相談することが重要です。
圧迫や外傷を避ける
シャントがある側の腕で血圧を測定したり、採血をしたりしないように注意が必要です。また、腕時計をしたり、腕にバッグをかけたり、重い荷物を持つこともシャントを圧迫し、血流を妨げる原因になるため避けましょう。
定期的な検査
ご自身のケアに加えて、医療機関では超音波(エコー)検査や血流量の測定などを定期的に行い、トラブルを早期に発見することが大切です。ブラッドアクセスが完全に詰まってしまう前に適切な治療につなげられるようにしましょう。
・公益社団法人日本臨床工学技士会 バスキュラーアクセス管理委員会臨床工学技士のためのバスキュラーアクセス日常管理指針
・熊本県CKD看護研究会 バスキュラーアクセスについて
まとめ
透析に欠かせないブラッドアクセスには、内シャント・人工血管グラフト・カテーテルといった種類があります。それぞれに特徴があり、血管の状態や透析導入の緊急度によって適切な方法が選ばれます。
一度作ったブラッドアクセスも、日常のケアを怠れば閉塞や感染といったトラブルを招きかねません。毎日の観察や清潔保持、シャント側の腕を大切に扱うことが、透析治療を安定して続けることにつながります。ご自身のブラッドアクセスについてよく知り、医療スタッフと連携しながら大切に管理していきましょう。
※コラムに関する個別のご質問には応じておりません。また、当院以外の施設の紹介もできかねます。恐れ入りますが、ご了承ください。
※当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。