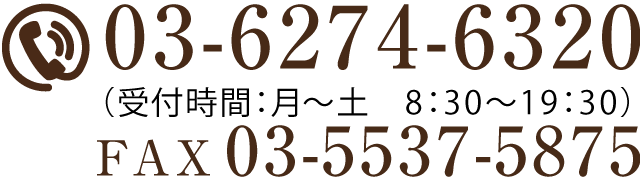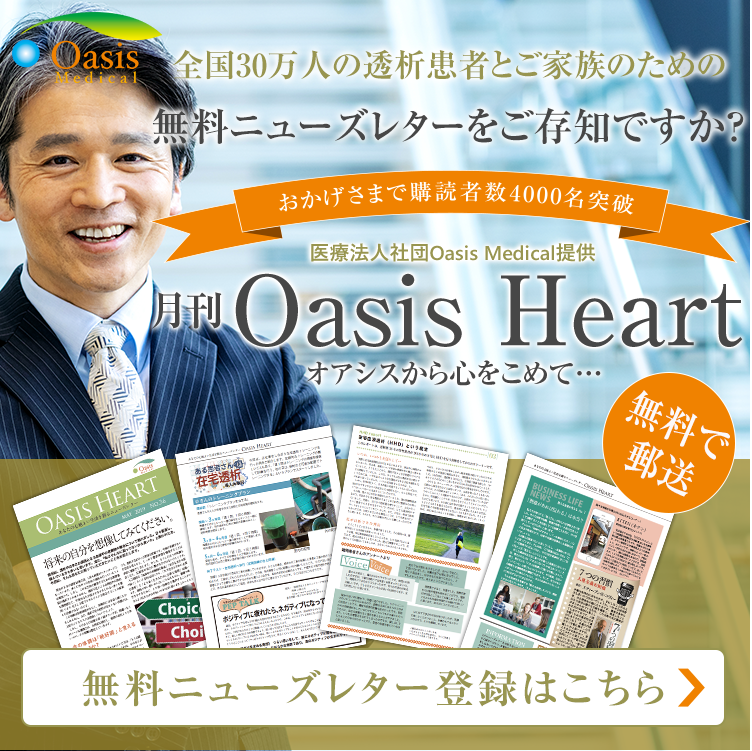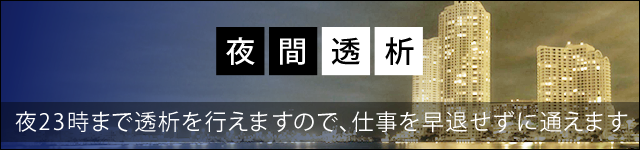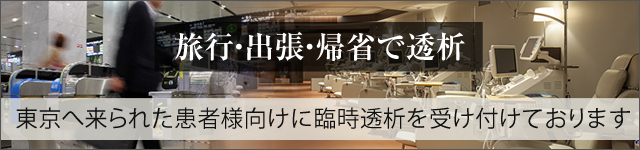透析患者とHIT(ヘパリン起因性血小板減少症)|知っておきたい症状と治療
透析治療では、血液の凝固を予防する目的でヘパリンという抗凝固薬が日常的に使われています。しかし、このヘパリンがHIT(ヘパリン起因性血小板減少症)という思わぬ副作用を引き起こすことがあります。本記事では、透析患者さんやご家族が知っておくべきHITの症状、原因、治療について解説します。HITについて知っておくことで、早期対応につなげましょう。
HITについて
血小板が減少し、血栓ができて血栓塞栓症を引き起こすこともあります。血液で流された血栓がふさぐ血管によって病態はさまざまで、冠動脈を閉塞すると心筋梗塞、脳の動脈をふさぐと脳梗塞、足の静脈をふさぐと下肢静脈閉塞症となります。

HITはI型とII型に分けられますが、主に問題となるのはⅡ型です。ヘパリンに対する抗体の産生により血小板が活性化し、消費されて減少します。活性化された血小板はトロンビンという酵素をどんどん作るようになり血栓症を引き起こすというメカニズムです。
HITと透析患者との関係
透析患者さんは、血液回路内での凝固を防ぐ目的でヘパリンを定期的に使用する機会が多いため、HITを発症するリスクがあります。Ⅱ型HITは一般的にヘパリン使用後5〜14日以内に発症するとされており、これまでにヘパリンを使用した経験がある患者さんほど注意が必要です。
Ⅱ型HITの発症頻度は0.5~5%と高くはありませんが、透析患者さんが使用を避けられない薬剤を用いていることを考えると、HITに早期対応できるように知識を得ておくことが大切です。
HITになるとどうなる?主な症状と影響
HITの特徴は血小板減少と血栓形成が同時に起こる点です。通常、血小板が減少すると出血しやすくなると思われがちですが、HITの場合は血栓ができやすくなり、重篤な病態を引き起こす恐れがあるため、大きなリスクとなります。

Ⅱ型HITではヘパリン投与開始から5~14日での発症が多い傾向がありますが、投与後1日以内に発症する場合もあります。
HITでみられるのは血小板減少症と動静脈血栓症です。
- 血小板減少症:患者さんのほとんどに見られる症状です。青あざ、鼻血などの出血症状が挙げられますが、出血症状がみられない場合もあります。血小板は発症前の30~50%にまで減少します。
- 動静脈血栓症:血栓塞栓症を引き起こすことがあり、動脈よりも、深部静脈やカテーテルでの塞栓症が起こりやすいとされています。
- 透析血液回路内の凝固:透析患者さんのHIT発症を疑うポイントとなります。
透析中にHITと診断されたらどうする?
透析中にHITが強く疑われた場合は、抗体検査を待たずに、直ちにヘパリンを中止し、アルガトロバンなどの非ヘパリン系抗トロンビン薬の投与を迅速に開始します。透析回路内の凝固防止には、回路内投与と持続投与を組み合わせ、凝血や止血状況を見ながら調整が必要です。
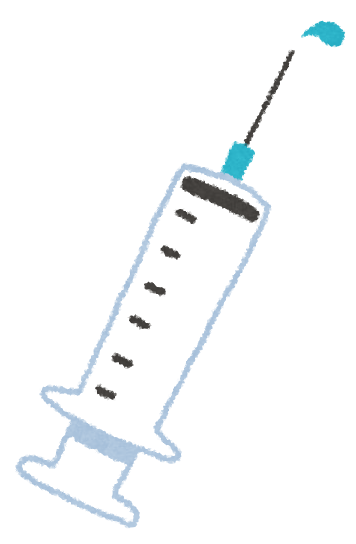
ヘパリン中止のみでは血栓リスクが残るため、過剰なトロンビンを除去する目的で抗凝固療法を継続する必要があります。
まとめ
HIT(ヘパリン起因性血小板減少症)は、透析に使われるヘパリンという薬によって血小板が減り、血栓ができやすくなる病気です。重症化を防ぐには、早期の発見と適切な対応が不可欠です。HITの頻度は多くありませんが、正しい知識を持っておくことで早期発見・適切な治療につながります。
透析患者さんやご家族は「青あざや鼻血など、出血しやすくなっていないか」「透析中に回路がつまることがないか」「定期検査で血小板が減っていると言われたことがないか」を注意し、気になる症状があれば主治医や医療スタッフに伝えましょう。
※コラムに関する個別のご質問には応じておりません。また、当院以外の施設の紹介もできかねます。恐れ入りますが、ご了承ください。
※当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。