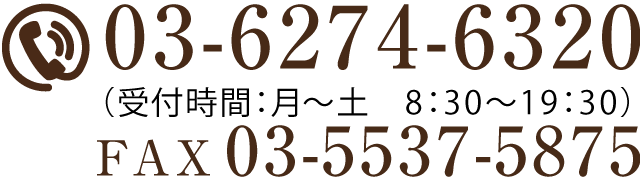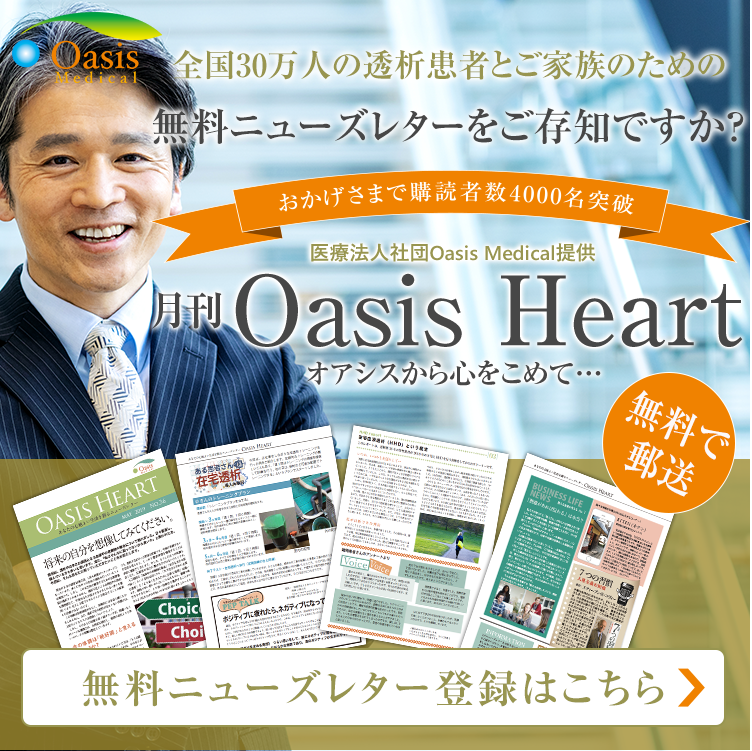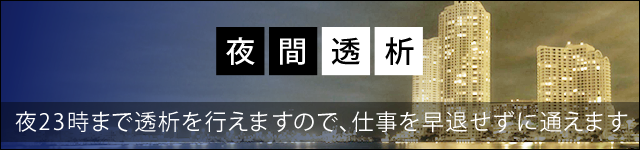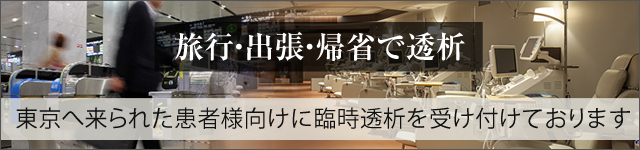透析は月1回でできる?標準的な回数と医師に通う頻度の違い
これから透析治療を始める方や、ご家族が透析を検討されている中で、「透析は月1回」と耳にしたことがある方もいるかもしれません。しかし、透析患者さんの通院回数とは異なります。この「月1回」が示すのは、多くの場合、透析治療ではなく、定期的に行われる医師の診察や検査を指しています。
この記事では、血液透析の基本的な治療回数と「月1回」の医師の診察、実際のスケジュール例などについて解説します。

透析の基本的な回数
透析の基本的な回数は、週3回です。体内に溜まった老廃物や余分な水分は、腎臓が正常に機能していれば24時間休むことなく尿として排泄されます。しかし、透析治療では、次の治療までの間に老廃物や水分が体に溜まってしまうため、溜まった水分や老廃物を透析治療で除去しなければ命にかかわる状態となります。
週3回が、死亡リスクを避けるための標準ラインとされています。1回の治療時間は、患者さんの体格や状態によって異なりますが、日本透析医学会では、週3回の透析では最低限4時間以上を推奨するとされています。
「月1回」とは医師の診察のこと
「透析は月1回」という言葉を耳にしたとしたら、それは多くの場合、透析治療そのものではなく、月1回定期的に行われる医師の診察や、それに伴う検査を指します。
安定して効果的な透析治療を継続するためには、治療が適切に行われているか、合併症の兆候がないかを定期的に評価することが不可欠です。月1回の診察で、透析患者さんの体調を総合的に把握し、今後の方針を立てるためにも役立ちます。
診察時には、主に以下のような検査が定期的に行われます。
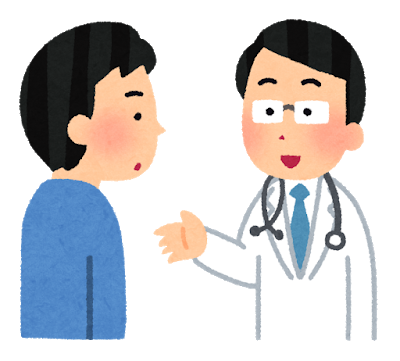
透析量の評価
透日本透析医学会維持血液透析ガイドラインでは、尿素がどれだけ除去できたかを示す指標(Kt/V urea)を用いて、透析量を月1回以上測定することが推奨されています。バスキュラーアクセスの不具合などで透析効率が落ちていないかを確認するため、月1回のチェックは重要です。
定期的な検査
透析時の目標体重となるドライウエイト設定の指標に関する項目を中心に、以下のような検査が行われます。
血液検査
透析量の評価に加えて、貧血の状態(ヘモグロビンなど)、栄養状態(アルブミンなど)、ミネラルバランス(カルシウム、リン、カリウムなど)を調べます。
胸部レントゲン検査
心臓の大きさ(心胸郭比)や、肺に水が溜まっていないか(肺うっ血)などを確認し、体液管理が適切に行われているかを評価します。
心電図検査
心臓への負担や不整脈の有無などを定期的にチェックします。
身体所見
血圧測定や、浮腫(むくみ)がないかなどを確認します。
「月1回」とは、主にこれらの定期的な診察や検査を指しています。腹膜透析の月1~2回程度の通院を指している場合もあるでしょう。
透析患者の通院スケジュール例
血液透析を受けている患者さんの1ヶ月の基本的な通院スケジュール例を紹介します。多くの場合、週3回の透析治療日に合わせて、月1回の診察や検査が組まれます。
下記は、月・水・金に透析を受ける場合のスケジュール例です。月1回の定期診察日は第一月曜など設定されている場合もありますが、医療機関によって異なります。

| 通常の透析日(例:月・水・金) | 月1回の定期診察(例:第一月曜など) |
|---|---|
|
|
まとめ
血液透析において耳にすることのある「月1回」とは、治療の頻度ではなく、血液透析の安定した継続に不可欠な定期的な医師の診察や検査を指している場合がほとんどです。
また、自宅での治療が中心となる腹膜透析も、通院は月1〜2回程度のため、この通院を指して「月1回」と言われることもあります。透析における「月1回」という言葉は治療そのものではなく、医師による定期的な診察・検査を指すことが多いと理解しておきましょう
※コラムに関する個別のご質問には応じておりません。また、当院以外の施設の紹介もできかねます。恐れ入りますが、ご了承ください。
※当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。